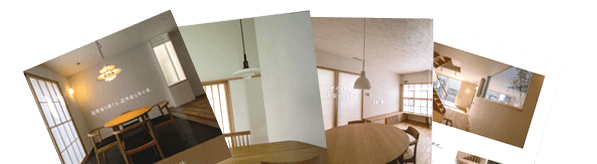- 代表ブログ
戸建て住宅省エネ基準義務化・四号特例の縮小で、今後の家づくりにどう影響する?

2025年4月に、建築基準法が改正されます。
具体的には、戸建て住宅の省エネ基準義務化と、四号特例の縮小などです。
これらの改正は、住まいの省エネ性向上と安全性の確保が目的とされていますが、これから家を建てる人にどんな影響を与えるのでしょうか。
今回は、2025年4月の法改正による戸建て住宅省エネ基準義務化、そして四号特例の縮小に関するお話です。
建築基準法改正により変わること
2025年4月の建築基準法改正により、家づくりに影響する3つの変更点をピックアップしました。
- 省エネ基準の義務化
- 四号特例の縮小
- 構造計算基準の合理化
では、今後の家づくりに影響する3つの変更点についてくわしくご紹介します。
①省エネ基準の義務化
法改正により、すべての新築建造物に対して省エネ基準へ適合することが求められます。従来との違いについては、以下をご覧ください。
| 法改正前 | 法改正後 |
|
|
家づくりに影響すること、それは広さを問わず省エネ基準に合致させなくてはならないという点です。
これまでは、省エネ基準に関する説明や届け出が必要でしたが、基準自体は合致させる必要がありませんでした。しかし、2025年4月以降に着工する新築住宅においては、広さを問わず省エネ基準に合致させる必要があります。
これにより考えれるのは、
- 確認の手順が増えること
- 竣工までの期間が長引く可能性
- 省エネ基準適合のための設備や資材の導入
などです。特に、省エネ基準適合のための設備や資材を導入するということは、建築にかかるコストが増える可能性を含んでいます。
一方で、省エネ基準に適合した住まいは、光熱費を節約できるメリットがあります。また、省エネ基準の義務化により、大幅な温室効果ガスの排出量削減に貢献できるのもポイントです。
②四号特例の縮小
2025年4月より、四号特例の縮小で平屋かつ延床面積200㎡以下の住宅(=新3号建築物)のみ、建築確認が省略できるようになります。
そもそも四号特例とは、以下の4号建築物に対し、都市計画区域内であっても建築士が設計を行う場合に、建築確認にて構造耐力関係規定等の審査を省略することができる特例です。
【4号建築物】
- 2階建て以下、延床面積500㎡以下、高さ13m・軒高9m以下のすべてを満たす木造建築物
- 平屋かつ延床面積200㎡以下を満たす非木造住宅
これまで、4号建築物は工事監理者(建築士)が設計書通りに施工されていることが確認できれば、構造耐力関係規定等の審査だけでなく、検査も省略することができました。
しかし、建築基準法における4号建築物の区分が廃止されることで、今後は「新2号建築物」「新3号建築物」という区分が新たに加わります。
- 新2号建築物:木造2階建てまたは木造平屋建て、かつ延床面積200㎡超
- 新3号建築物:木造平屋建て、かつ延床面積200㎡以下
つまり、小規模住宅の新3号建築物においては、従来の4号建築物同様に建築確認が省略され、新2号建築物においては審査項目が新たに加わることになります。
ここで、法改正前・後の4号建築物と新2号建築物に対する審査項目について比較してみましょう。
| 法改正前
(4号建築物) |
法改正後
(新2号建築物) |
|
| 敷地関係規定 | 審査あり | 審査あり |
| 構造関係規定 | 審査なし | 審査あり |
| 防火避難規定 | 審査なし | 審査あり |
| 設備その他 単体規定 | 一部審査あり | 審査あり |
| 集団規定 | 審査あり | 審査あり |
| 省エネ基準 | (適合義務対象外) | 審査あり |
参考:国土交通省ホームページ
2025年4月の建築物省エネ法改正で、省エネ基準の適合が義務付けられるため、新2号建築物の建築確認申請の際は「構造・省エネ図書」の提出が必要です。新3号建築物の場合も、審査は省略されるものの「構造・省エネ図書」の提出が求められます。
家づくりに影響することと言えば、2階建て以上の住まい、もしくは延床面積200㎡以上の住宅(=新2号建築物)は、すべて建築確認が必要になるという点です。建築確認基準が必要な建築物も多いと想定されることから、従来よりも住まいの完成まで時間がかかる可能性もあるでしょう。
③構造計算基準の合理化
建築基準法の改正により、高度な構造計算なしで建てられる建築物の範囲が広くなります。おもな範囲や対象となる住宅については、以下を参考にしてください。
| 簡易的な構造計算のみで建築可能となる建物 |
|
| 仕様規定だけで建築可能となる建物 |
|
これまで、特定の基準を満たす木造建築物について、耐久性や耐震性を客観的に確認するために高度な構造計算が求められていました(許容応力度等計算、保有水平耐力計算など)。加えて、これらの建物は一級建築士以外に設計・工事監理ができないと定められていたため、対応できる建築士が少ないというデメリットがありました。
しかし、法改正により二級建築士が設計できる建築物の範囲が広がるため、より合理的な建築が実現可能となります。
家づくりにおいては、対応できる建築士が増えることで、従来よりもよりスピーディに、かつコストを抑えた建築が可能になると考えられます。
建築基準法改正によるリフォームへの影響
建築基準法の改正は、新築だけではなくリフォームにも大きな影響を与えます。主に考えられるのが、次のポイントです。
- 建築確認申請の手間が増える
- リフォームのコストが増える
まず、建築確認申請はリフォームやリノベーション、スケルトンリフォームを行う際も必要です。2025年4月の建築基準法改正では新たなルールが加わるため、確認申請の手間が増えることになります。
もちろん、建築確認申請の多くは設計事務所が代行することがほとんどなので、建築主に直接影響するわけではありません。しかし、手間が増えることで建築確認申請に時間がかかると、施工までに時間がかかることもあるでしょう。
※ただし、大規模改修に該当しないような屋根、外壁などのリフォームは建築確認申請が免除されるケースもあります。
そして、建築確認申請によりリフォーム費用が増えることが予想されます。もしも図面のない物件なら、天井や壁を剥がして内部を調査しなくてはなりません。さらに、間取りを大幅に変更する場合も、今後は建築確認申請が必要となります。
建築基準法改正後の基準に適合していなければ、適合させるための追加工事も必要なので、これまで以上にリフォーム費用がかかることもあるでしょう。
建築基準法改正の背景とメリット
今回の建築基準法改正には、次の目的があります。
- 省エネ対策
- 木材の利用促進
- 建物の倒壊防止
近年、省エネへのニーズが高まりつつあります。政府においても、2030年度における温室効果ガス46%削減や、2050年のカーボンニュートラル達成を目標に掲げ、建築物における省エネルギー対策を強化しています。
建築基準法においては、エネルギー消費性能に関する基準が段階的に引き上げられており、より高い省エネ性能が求められているのが現状です。今回の法改正でも、省エネ対策を促進する規制が新たに設けられた形となります。
さらに、木材には温室効果ガスを吸収する効果があります。建築において木材の需要は非常に高いことから、建築物の木造化を進めることで省エネ対策につなげる目的があるのです。
住まいにおける省エネ対策が成功すれば、電気代やガス代などのエネルギーコストを減らすことができ、家計の負担も軽くなります。さらに、国際社会における環境問題に貢献できるというメリットも生まれます。
そして、建築基準法改正の目的は省エネ対策だけではありません。
これまでの四号特例という制度では、一部の建物で構造計算のチェックが省略されており、地震などで倒壊するリスクが十分に確認できていない建物がありました。今回の改正により四号特例を縮小することで、チェックが省略されていた建物についても、建築確認審査が義務付けられるようになります。
これにより、建物自体の安全性が高まり、安心して暮らせる住まいが増えることが期待されます。
建築基準法改正により家づくりで注意したいポイント
法改正により省エネ住宅の促進や、木造住宅の建築を後押しする法整備が期待されますが、注意したいポイントもあります。それは建築コストとスケジュールに関する問題です。今後家づくりを始める人に知ってほしい、法改正後の注意点についてくわしくご紹介しましょう。
建築コストの増加に備え優先順位を決めておく
法改正では、確認事項が増えるのはもちろん、省エネ基準を満たした住まいを建てなくてはならなくなるため、従来よりも建築コストが増加すると予想されます。
たとえば、建築確認申請が必要な2階建て以上の住まい、もしくは延床面積200㎡以上の住宅(=新2号建築物)の場合、構造計算書作成の費用だけでも20~30万円程度かかります。事前に予算を決めても、想像以上に見積もり金額が高くなるケースもあるでしょう。
予算オーバーを防ぐためにも、家づくりにおいてこだわりたい部分に優先順位をつけておくと安心です。
また、法改正の内容を正しく理解し、信頼できる建築会社に相談することも大切です。建築基準法だけでなく、家づくりにかかわるさまざまな法律は、不定期に改正されています。法規制を熟知した建築会社に依頼しなければ、建築許可が下りない、また着工までの時間が長引く可能性もあります。
法改正に関する知識や実績、提案力があり、かつ補助金や助成金を熟知している建築会社を検討してください。
スケジュールには余裕を
法改正により四号特例が廃止されると、2階建て以上の住宅、もしくは延床面積200㎡以上の住宅(=新2号建築物)は、すべて建築確認が必要になります。また、広さや建物用途に関係なく、すべての建築物に対し省エネ基準に合致させなくてはならないため、確認事項が長引くことが予想されます。
このような事情から、建築申請に時間がかかる可能性があるため、当初予定していた時期に着工できないというケースもあるでしょう。もし、引っ越しや進学に合わせて新築住宅の入居時期を決めているなら、余裕を持ったスケジュールを組むようにしましょう。
法改正や補助金制度に熟知した真柄工務店にお任せください
家づくりにはさまざまな法律が絡みますが、専門家でない限りすべてを理解するのは難しいものです。真柄工務店では、建築基準法をはじめとする法律関係について常にアップデートをし、お客様に最新の情報をご提供します。
また、複雑な補助金制度や助成金制度においても、お客様一人ひとりの状況に合わせて最適なご提案や代理申請が可能です。お客様が安心して家づくりを進めていただけるよう、真柄工務店が全力でサポートいたします。
信頼できる建築会社選びにお悩みなら、ぜひ真柄工務店にお任せください。
まとめ
あらためて今回の内容をおさらいしましょう。
2025年4月の法改正により、主に以下の内容が変更されます。
- 省エネ基準の義務化
- 四号特例の縮小
- 構造計算基準の合理化
これにより、建築スケジュールに遅れが生じたり、建築コストが増加したりと、家づくりで注意すべきポイントも浮き彫りになります。安心して家づくりを進めるなら、余裕を持ったスケジュールを組み、優先順位を決めておくことがポイントです。また、法改正に熟知した建築会社に依頼することで、やりとりもスムーズになるでしょう。
信頼できる建築会社をお探しなら、真柄工務店へ。法律や補助金制度などに熟知したスタッフが、お客様の家づくりを全力でサポートいたします。